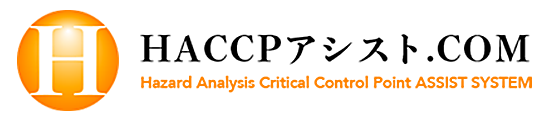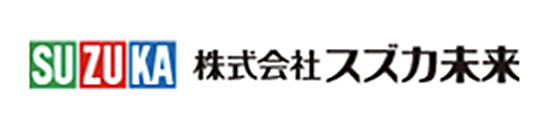食品添加物 “無添加” 表示、何がダメ? 禁止例を解説!
いつも食品表示サポート.comをご覧いただきありがとうございます。2024年4月から、消費者庁より施行された『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』では、
食品添加物の「無添加」「不使用」表示によって消費者へ誤解を与えないためのルールが定められました。
このガイドラインでは、注意すべき表示パターンを10類型に分類し、それぞれに対して具体的な禁止事項が定められています。
【「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスター(両面)|消費者庁】
【「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の10類型イラスト|消費者庁】
10類型の内容を、NG表示例とともに解説いたします!
類型1:単なる「無添加」の表示
→何が無添加なのか、対象が書かれていないと、誤解のもとに。
「添加物」だけでは、添加物が一切使用されていないように誤解させる恐れがあります。
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
→例:「人工甘味料不使用」「合成着色料無添加」など。
法律上規定されていない用語(人工・合成・化学・天然 等)を使うと、実際よりも安全・健康的と誤認させる恐れがあります。
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
→例:ごまに「次亜塩素酸ナトリウム不使用」など。
※ごまに次亜塩素酸ナトリウムを使用することは禁止されています。
そもそも使用できない添加物を、「無添加」「不使用」と表示することは不適切です。
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
→例:「保存料無添加」と表示しつつ、日持ち向上の目的で「グリシン」を使用。
実質的に同じ効果がある添加物を使用しているにも関わらず、無添加であるように見えて、他商品よりも安全・健康的と誤認させる恐れがあります。
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
→例:「調味料(アミノ酸等)無添加」と表示しているが、食品の原材料にアミノ酸を含む抽出物である酵母エキスが含まれている。
原材料に同様の機能をもつものがあれば、注意が必要です。
類型6:健康、安全と関連付ける表示
→例:「着色料無添加で体にやさしい」「保存料不使用だから安全」など。
添加物は国の安全評価を経て使用が認められています。無添加・不使用を根拠に「健康」「安全」と結び付ける表示は、実際よりも優れていると誤認させる恐れがあります。
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
→例:「化学調味料無添加だからおいしい」など。
科学的根拠なしに関連付けると、実際よりも優れていると誤認させる恐れがあります。
→例:「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください(開封後と記載なし)」など。
消費・賞味期限よりも早く食べなければならないという印象を与え、期限表示と矛盾する恐れがあります。
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
→例:ミネラルウォーターに「着色料無添加」と表示。
もともと添加物を使用しないことが一般的である食品に、無添加・不使用を表示すると、実際よりも優れていると誤認させる恐れがあります。
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
→例:弁当の製造過程では添加物不使用だが、原材料の醤油には保存料が使用されているにも関わらず、「保存料無添加」と表示(キャリーオーバーに該当)。
→例:惣菜の原材料であるカット野菜に、漂白剤が使用されていないことが確認できないにも関わらず、「漂白剤不使用」と表示(加工助剤に該当)。
加工助剤やキャリーオーバーについても確認が必要です。実際と異なる表示を行うと、内容物を誤認させる恐れがあります。
類型10:過度に強調された表示
→例:容器包装のあらゆる箇所に、大きく「○○無添加」「○○不使用」と表示。
目立ちすぎると、他の表示(一括表示)を見る妨げとなる恐れがあります。また、表示上の添加物だけでなく、すべての添加物を使用していないと誤認させる恐れがあります。
「無添加」「不使用」などの表示は、商品価値を高める一方で、消費者へ誤解を与える可能性もあります。
ガイドラインの内容をしっかり理解し、正しい表示を心がけましょう!